
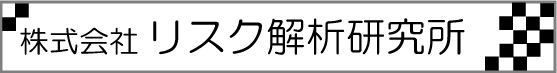
 |
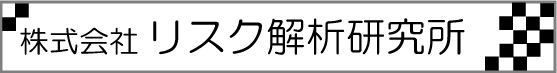 |
|
|
|||
| 戻る | |||
|
ラット発がん実験とPBPKモデルによるダイオキシンのリスク解析
|
|||
|
考え方
|
現在,世界中のどの地域でも,大気や土壌や河川からダイオキシンが見つかります。 私たちは大気や水や食品から日常的に微量のダイオキシンを体に取り込んでいる(95%以上が食品由来)ので,1回に食べる量は微量ですが,その慢性影響が気になります。
毎日取り込んでいるダイオキシンがどのくらい蓄積して,がんを発生させる可能性があるかを,コンピューターで計算する事ができます。 この方法は,長期慢性影響を予測する方法として,疫学や動物実験に代わり,最近注目されています。 |
||
| ダイオキシンの発がんリスクは,次の方法で計算できます。[参考文献1] | |||
|
Step 1
動物実験 |
ラットを使ったダイオキシンの発がん実験を行います。 ラットにある種の発がん物質を与えた後,ダイオキシンを数ヶ月与え続けて人工的に肝臓がんを起こします。 この方法は,発がん促進作用をもつ物質の毒性を測るための方法として,よく用いられています。[参考文献2] | ||
|
Step 2
体内濃度推定 |
一方,動物や人の体内にどのくらいのダイオキシンが蓄積するか予測します。 実験動物の場合は,実際に臓器を採取して測定する場合もあります。 人の場合はコンピュータによるシミュレーションを行います。 このとき使うのは,PBPKモデルという方法です。(PBPKモデルについて) | ||
|
Step 3
曝露量推定 |
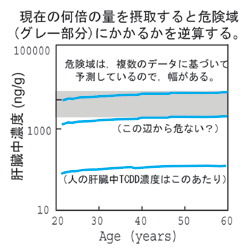 |
||
| 物質の毒性を考えるとき,その物質が主に悪さをする臓器,すなわち”標的臓器”をメインに定量評価をする,という一つの方法があります。
ここでは,標的臓器として肝臓に着目してみましょう。 がんが発生した時のラットの肝臓中ダイオキシン濃度を参考に,人で同じ濃度に達するためには,どのくらいのダイオキシンを摂取しなければならないのかを逆算します。 こうして得られた摂取量が,いわば人に対する危険摂取量となります。 現在の摂取量がこの危険摂取量の何%に相当するか,といった解析を加えることで,現状のリスクがわかります。 上の図は,ダイオキシンのうち最も毒性が強いと言われる2,3,7,8-TCDDという種類のダイオキシンの場合です。 |
|||
| 他の29種類に関してはデータ不足ですが,ダイオキシン類は物性が似ていると考えられるので,上記の方法で同じようにリスクを計算することができます。 | |||
|
参考文献
|
文献1:Maruyama W, Aoki Y.(2006) Toxicol.Appl.Pharmacol. 214:188-198 文献2:Ito N et al.(1988) Carcinogenesis 9:387-394 |
||
|
[an error occurred while processing the directive] |