
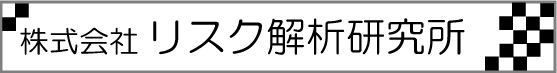
新たな方法
↓
人の毒性評価
さてこのデータはあくまでラットの物ですから,これを人の場合に変換しなければなりません。 ここでダイオキシンのリスク評価と似た方法,すなわち”標的臓器に着目した,毒性換算方法”を用います。(ダイオキシンのリスク評価はこちら。)
ここでは標的臓器は”肺”です。 肺に蓄積する粒子の量と,肺ガンの量的関係をラットで調べ,その結果をもとに人の肺ガンリスクを算出してみます。 実際の計算には,様々な数値処理と複雑なコンピューター・シミュレーションが必要ですが,ここではあまり詳しい計算は述べません。 詳細に興味がある方は論文(文献1)をご覧下さい。
発がんリスク
他の研究報告をみると,100人中2人(文献2),1万人に4人(文献3),10万人に2人(文献4)など,かなり高い危険性を見積もっています。 疫学ベースで計算すると,動物実験からの外挿に比べて100倍以上のハイ・リスクになる傾向があります。
環境省の平成16年の調査によれば,大気中の粒子(粒径が揃っていませんが)の量は平均36-46mg/m3ということです。 そうすると単純計算では,自動車排ガス粒子のせいで肺ガンにかかる人の割合は,日本でだいたい10万人中2〜4人程度です。 ちなみに日本全国で肺ガンが確認された人の割合は,1万人に2人程度です。 この中には,喫煙その他の原因で発症する人も含まれていますので,排ガス粒子の責任はだいたい全体の1/10というところでしょうか。
さて,皆さんはこの結果を見て,「ディーゼル排ガス粒子はやっぱりとても危険だ」と思われますか? それとも,「意外にリスクは低いな」と思われますか?
文献2:Schwartz J. and Dockery D.W. (1992)Am.Rev.Respir.Dis. 145 :600-604
文献3:岩井ら(1992) 大気環境学会誌 27 :296-303
文献4:WHO (1996) EHC171 :231-286
[an error occurred while processing the directive]