
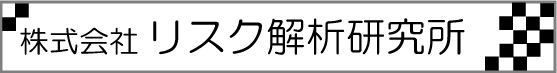
 |
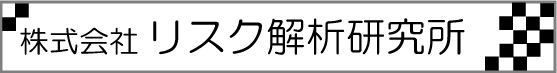 |
|
有害性はどうやって決める?
|
|||||
|
ハザード?
|
”ハザード”に対する決まった和訳は今のところありませんが,リスク評価研究の分野では一般に”有害性”と解釈されています。 ハザードを「有害性」の意味で使う場合は,定性的側面だけを考える場合が多いようです。 しかし「リスク=ハザード×曝露」などといった場面では,定性的概念とともに定量的概念をも含んで用いられるので,注意が必要です。 | ||||
|
基本は
毒性学 |
有害性評価には毒性学が必要です。 関連の学問分野は,医学・薬学などです。 毒性学上の研究や実験データから,物質が体のどこに作用し,致死的作用や疾患を引き起こすか,など有害性に関する情報を得ることが出来ます。 | ||||
|
体内の毒性の発生メカニズムを調べる研究も,有害性評価に分類されます。 また,個人の曝露レベルでの被害程度を算出する研究も,ハザード解析に含まれます。
|
|||||
|
方 法
|
毒性研究,特に化学物質の毒性は,主に実験動物(マウスやラット)を使って研究されます。 また時には疫学によって,人での悪影響が先に発見される場合もあります。しかしいずれにせよ,環境中の化学物質の中には,まだその毒性がよくわかっていないものもあり,引き続き世界中の研究者によって実態解明が続いています。 | ||||
|
|||||
| ★疫学的アプローチと動物モデル★
上の左の図は疫学を,右の図は動物実験データをもとに,ある物質Aの毒性評価を行う手順です。 疫学の良い点は最初から人のデータを使っているので,量の換算を必要としないことですが,一方で毒性の検出感度が良くないという欠点があります。 動物データを使う方法は,細かい毒性のメカニズムがわかる事と微量の毒性も検出できる点ですが,動物を使っているので,最終的に人への換算が難しいことが最大の欠点です。 |
|||||
|
[an error occurred while processing the directive] |
|||||