
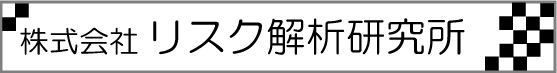
リスク評価に関する専門家向けページ
リスク評価の手順について
概 要
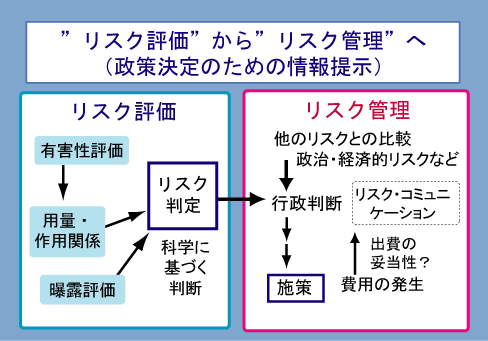
1)有害性評価,2)用量−作用関係評価,3)曝露評価です。
1)と2)を合わせて有害性評価(ハザード評価)と考える場合もあります。
リスク評価の簡単な手引き書では,リスク=ハザード×曝露 などと書かれています。
以下,3つのプロセスを順に説明します。
有害性評価は最初に必要なプロセスです。 有害性を確認する方法は主に動物実験ですが,まれに人の被害が先に発生して,有害性が確認される事もあります。
有害性評価の次に,用量−作用関係評価(Dose-response assessment)を行います。
用量という言葉は,薬の服用量を表す"DOSE"からきていますが,環境リスク評価の分野では同じ言葉を動物の体内量という意味でも使います。
このプロセスは,体内の有害物質の量と,その時の悪影響の大きさの関係を把握する作業です。 量−作用関係の基礎データは,規制のレベルなどをどの位にしたら適切か検討する際の重要な根拠となります。
問題となる有害物質を,人が実際にどの位取り込んでいるかを把握するプロセスです。
これはリスク評価の最終段階として,現状のリスクを算出するために必要です。
[an error occurred while processing the directive]