
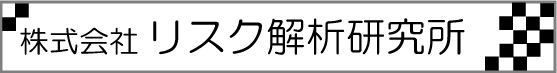
 |
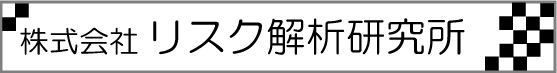 |
| 用語解説1 前のページ | |||
|
PBPKモデルの詳細
|
|||
|
いつから
注目されたか |
PBPKモデルの手法自体は,すでに1930年ごろには提唱されていたようですが,1980年代に揮発性有機物の濃度を動物から人へと外挿するモデルが作られて以来(文献1),環境科学への応用が注目されました。 毒性を持つ化学物質が環境中にある場合,それが人の健康にどの程度影響するのかを調べるため,その方法として注目されてきたのです。 | ||
|
なぜ注目
されているか |
普通,毒性のデータは動物実験から得られます。 これを人間の場合に当てはめる場合,マウスやラットなどの実験動物と人間の,体の違いを考慮して換算しなければなりません。
換算方法として最も簡単なのは,体重と曝露量だけを使う方法ですが,これだと不十分です。 なぜなら,動物と人間は臓器の体重比が異なるので,単なる体重換算だと,臓器ごとの物質濃度の推定に,大きな誤差が出てきます。 それに加えて,物質の代謝速度や感受性に動物種差がある場合,その分も考慮しなければなりません。 |
||
| 下図に,PBPKモデルの構造と数式の例を示します | |||
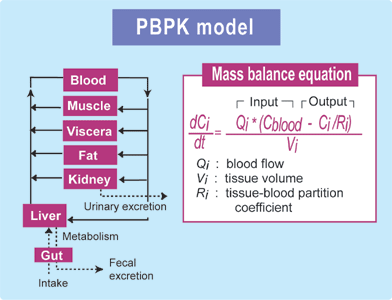 |
|||
| PBPKモデルでは上図に従って,体内の組織重量や,組織の血流量・代謝速度などの情報をシミュレーション・プログラムに組み込みます。
図の右側にある"物質バランス式(mass balance equation)"は,ある1つの臓器に着目した場合の,その臓器における物質の出入りを表した式です。PBPKモデルではこのような式を臓器ごとに作り,その連立方程式を解く形で計算します。 |
|||
|
最近では。。
|
最近,本家の薬学領域で用いられているのは,PBPD(physiologically based pharmacodynamic model)というモデルです。 PBPKとPBPDは途中まで同じですが,解析の掘り下げ方に違いがあります。 PBPKでは,臓器中濃度の解析だけに留まるのに対し,PBPDでは,同じ濃度による応答の違いにも焦点をあて,さらに細かい解析を行います。 例えば,物質が大人の肝臓と子供の肝臓に同じ濃度で存在しても,分解能力の弱い子供の肝臓では,作用が強く出る,などの解析は,PBPDに属する解析となります。 ただし,環境リスク評価分野の解析では,まだPBPDを適用するほどの細かい解析は必要ないようです。 |
||
|
|
|
||
|
参考文献
|
文献1:Ramsey & Andersen (1984) Toxicol.Appl.Pharmacol.(スチレン) 文献2:Lawrence & Gobas (1997) Chemosphere (ダイオキシン) 文献3:Clewell et al. (2000) Environ. Health Perspect. (TCE) 文献4:Maruyama et al. (2002) Toxicol.Environ.Health A (ダイオキシン) このほか多数の論文あり。最近,英語の専門書も出版されました。 日本語の参考書は,残念ながらまだありません。 |
||
|
[an error occurred while processing the directive] |
|||